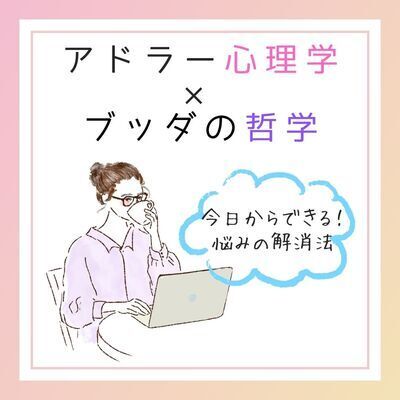☑毎日が同じことの繰り返しに感じる。新たな刺激がほしい
☑ 今までない学びを得て、スキルアップや、いい人間関係づくりに役立てたい
☑ 職場以外の友達がほしい
そんな気持ちに応えられるよう、
この勉強会では、いろいろな職種の方が参加されて交流を深めていただくとともに、
日常に生かせる心理学を紹介します。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆
今回のテーマは、
ブッダとアドラー心理学に学ぶ「“不健全な劣等感”を克服する方法」
です。
「劣等感」と聞くと、どんなイメージを持たれるでしょうか?
「自分の成長をじゃまするもの」
「劣等感のある自分はダメな人間だ」
と、悪いイメージを持たれている方が多いと思います。
ところが アドラーは、
「劣等感を抱くこと自体は不健全ではない。
目標がある限り劣等感があるのは当然なのだ」
と、劣等感は健全なものであり、目標達成の原動力になると語っています。
このように劣等感そのものは健全なのですが、
問題は、この劣等感をどう使うかです。
使いようによっては不健全なものになり、私たちを苦しめることになるのです。
劣等感を目標達成のバネにするか、
あるいは、できないことの言い訳に使うかの分かれ目は
「自己受容ができているかどうか」です。
ワークショップでは
- 「不健全な(強すぎる)劣等感」とは何か?そのメカニズム
- どうすれば不健全な劣等感を克服して、目標達成・自己理想へと近づいていけるのか?
をお話しします。
また、ブッダの説かれた教え(仏教)にも、
「“不健全な劣等感”の克服法」がいくつか説かれています。
ワークショップではアドラー心理学と仏教の両方の観点から、
不健全な劣等感を克服する方法をご紹介します。
アドラー心理学と仏教、合わせて学ばれることで
両方の理解がより進まれるでしょう。
<勉強会の内容>
◯「劣等感を抱くこと自体は不健全ではない」といわれる理由
◯あなたを苦しめる“不健全な劣等感(=劣等コンプレックス)”とは?
◯これを使っている人は要注意!
劣等コンプレックスの人の2つの口癖
◯マイナスをプラスに変えた偉人のエピソード
◯不健全な劣等感を克服する3つの方法
欠点は使いようによっては長所減点方式から加点方式へ不合理な自己理想との決別
<参加された方の声>
アドラー心理学の本を読んではいたけど、具体的にイメージできていなかったので、今日の話を聞いて、具体的に理解することができました。
プレゼンの仕方がとても上手で、聞いていて全く飽きなかったです。
(20代・女性)
名前だけ知っていたアドラーについて、何を言っている人なのか知ることができました。
講師の語り口が穏やかで、聞いていてラクでした。
(30代・男性)
<タイムテーブル>
・自己紹介タイム
・プレゼンターからの話
・フリートーク、次回案内
<参加費>
500円+各自の飲食代
<プレゼンター>
はる
2014年 心理学部 卒業
2016年 大学院修士課程 修了(基礎心理学・応用行動分析学・ACT)
職種:カウンセラー
資格:公認心理師
大学と大学院で心理学を専攻し、
行動分析学や認知行動療法の分野を中心に学びました。
子どもから大人の臨床まで。
オンラインやカフェなどで個別の相談にも乗っています。
心理学よりも人間の”心”について深く解き明かしている仏教に出会い、
簡明を受けて学んでいます。
仏教で説かれるブレない“人生の指針”を伝えたいと思い、
心理学や自己啓発を切り口に、名古屋でワークショップやカフェ会を開催。