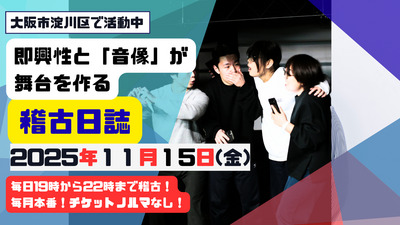
即興性と「音像」が舞台を作る〜観客と共演者に意識を向ける演技の追求〜
「セリフを言うだけじゃダメなんだ」——稽古場に響いた演出家の言葉が、役者たちの表情を引き締めた。
本日の稽古では、舞台上での「存在」そのものが問われる瞬間が何度も訪れました。共演者との関係性、観客との対話、そして舞台空間を立体的に捉える視点。演技における「音」と「位置関係」、そして「臨機応変な対応力」——この3つの要素が、どれほど舞台を豊かにするのか。その厳しくも熱のこもった指導の現場をレポートします。
1. 演技は「音像」で成立する——聞こえ方をデザインする技術
「アマチュアバンドのライブって、ボーカルが聞こえないことが多いでしょう?」
演出家が投げかけたこの問いに、稽古場がざわめきました。音楽と演劇——一見異なるジャンルですが、実は共通する本質があります。それが**「音像」**という概念です。
音像とは何か?
音像とは、音がどこから聞こえてくるかという立体的な位置情報のこと。演劇においても、セリフという「音」が観客にどう届くかをデザインすることが重要なのです。
稽古場での具体例:
-
最も伝えたいセリフの登場人物を一番前に配置する
観客は無意識のうちに、前方から聞こえる声を「重要な情報」として認識します。 -
立ち位置・角度・距離を変えることで、聴覚体験が変化する
ずっと同じ場所、同じ角度でセリフを言い続けると、観客も共演者も飽きてしまう。だからこそ、演出家は位置関係に厳しく注文をつけます。 -
「エモーショナルサウンド」の活用
ある役者が舞台前方に移動すると、後方にいる共演者たちは感情的な音(叫び声や泣き声など)を発しても、前方のセリフを邪魔しない——そんな選択肢が生まれることが指摘されました。
「音楽でミックスするように、舞台でも音を立体的に配置しろ」という演出家の言葉が印象的でした。
2. 「相手を最優先する思考」——傲慢な演技からの脱却
「相手の取った選択肢に対して拾うことしか考えていなかった」
ある役者がそう答えた瞬間、演出家の表情が変わりました。
「それは傲慢の俳優だ。ただボールを受け取っているだけじゃ、何も広がらない。拾って何するんじゃ?何を返すんじゃ?」
演技の核心は「自分」ではなく「相手」
この稽古場で繰り返し強調されるのは、演技の思考の中心が「自分」ではなく**「相手」**にあるべきだということ。
求められる思考プロセス:
「どのコミュニケーションのカードを切るか、考え続けろ。自分のことや感情を考えている暇は1秒もない」——厳しい言葉ですが、これこそがプロの現場です。
セリフが終わった後こそが勝負
「セリフが終わった瞬間に止まるな。切るな、続けろ」
セリフの終わりは行動の終わりではありません。次の展開へ体をどう繋げるか。共演者に「自分のセリフがないと移動できないのか?」という問いも投げかけられました。
また、距離の変化が役者自身の心を動かすという指摘も。常に同じ場所で同じ音を聞き続けていると、気持ちも動かない。だから、大きな声を出している相手に近づいたり、離れたりする——その動きが、役者の内面を活性化させるのです。
3. 「ビビり」は観客にバレる——動きの継続性と覚悟
「なんでさ、ひょこんひょこんて歩くの?普通に歩け」
「ビビってんじゃねえよ」
稽古の中盤、動きの不自然さが次々と指摘されました。
意図のない「停止」が多すぎる
役者たちの動きを観察していると、判断なく「止まる」瞬間が頻発していました。演出家は容赦なくそれを指摘します。
具体的な問題点:
- 不自然な移動 ——日常的でない動き方は、観客の没入感を削ぐ
- 中途半端な動き ——セリフに合わせて上半身は動いても、足が遅れる。これが「ビビっている」ことを観客にバラしてしまう
- 行動の遮断 ——セリフの後に「切っちゃう」ことで、次に起こるはずの面白い展開が潰れる
大きな動きをする際には覚悟が必要です。半端な動きは、舞台全体のリアリティを損ないます。
4. 「AからZまでの手札」——極限の応用力が求められる演出スタイル
「この演出は、めちゃくちゃ難しいんだよ」
演出家は自らそう語ります。それでも、このスタイルにこだわる理由があります。
一般的な劇団との違い
一般的な劇団:
動きや距離感を全て細かく決める。A、B、Cパターン程度の対応。
動きや距離感を全て細かく決める。A、B、Cパターン程度の対応。
この劇団:
全てを固定しない**「フリーダム」**な演出。AからZまでのプランが必要。
全てを固定しない**「フリーダム」**な演出。AからZまでのプランが必要。
なぜフリーダムなのか?
決められたプランが崩れた瞬間に、舞台全体が壊れることを避けるため。役者全員が多様な「手札」を持ち、臨機応変に対応できた方が**「リアルじゃん」**——そう演出家は語ります。
イマーシブな演劇体験
この演出家が作る芝居は「こういうものを見せます」というものではなく、「お客さんの反応ありき」。
例えば:
感動的なシーンで観客が予期せぬ場所で大爆笑した場合、従来のプランを無視して、その場の温度感に合わせて直感的に対応できる「手札」を選べることが求められます。
感動的なシーンで観客が予期せぬ場所で大爆笑した場合、従来のプランを無視して、その場の温度感に合わせて直感的に対応できる「手札」を選べることが求められます。
この訓練を積むことで、今回の作品だけでなく、他の作品でも応用が効くようになり、役者としての成長に繋がるのです。
【例え話】熟練シェフのキッチンに学ぶ、舞台の即興性
この稽古場で求められている臨機応変な対応力は、経験豊富なシェフがキッチンに立つことに似ています。
通常の料理人(A, B, Cパターン):
レシピ通りに作るが、食材の質やオーブンの調子など予期せぬ問題が起きた瞬間に手が止まってしまう。
レシピ通りに作るが、食材の質やオーブンの調子など予期せぬ問題が起きた瞬間に手が止まってしまう。
真の熟練シェフ(AからZを持つ役者):
その場で手持ちの技術と知識(手札)を使い、「これならこの距離でも使える」「今この客層ならこのアレンジ」と瞬時に判断し、料理(舞台)を最高の状態に持っていく。
その場で手持ちの技術と知識(手札)を使い、「これならこの距離でも使える」「今この客層ならこのアレンジ」と瞬時に判断し、料理(舞台)を最高の状態に持っていく。
決められたレシピ(台本)があっても、その日の材料(共演者の動き)や客の反応(観客の温度感)に合わせて、最高の一皿を作り上げる——それが、この劇団が目指す演技なのです。
おわりに:厳しさの先にある「面白さ」
この稽古場は、役者にとって極めて難しい環境です。しかし、その難しさが成長と面白さにつながっている——演出家自身がそう語っています。
観客と共演者に意識を向け、音像を意識し、AからZまでの手札を持つ。この3つの要素が揃ったとき、舞台は「生きた空間」へと変貌します。
次の稽古では、どんな化学反応が起こるのか。役者たちの成長が楽しみです。






