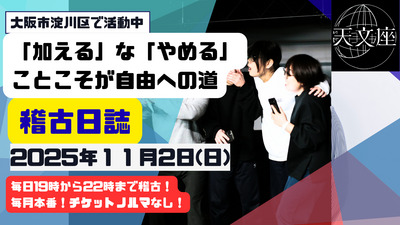
「加える」な「やめる」ことこそが自由への道
演技のパラダイムシフト:「ビア・ネガティブ」の衝撃
配役決定後の稽古では、演技に対する深いフィードバックが行われました。この指導の核となったのが、ポーランドの演出家イェジー・グロトフスキが提唱した、**「ビア・ネガティブ」(Via Negativa:否定の道)**という概念です。
「加える」演技の限界
演技指導の中で、俳優たちに対し、現状の芝居が「何かを加えてるのか」「何かを減らしてるのか」という問いが投げかけられました。
多くの俳優は、自然と「加える」という方向に意識が向きがちです。しかし、指導者はグロトフスキの哲学を引用し、**「何かを足すんじゃなくて何かを減らす」**べきだと強く主張します。
なぜ「加える」ことは難しいのでしょうか?
この考えは、インプロ(即興劇)の大家であるキース・ジョンストン氏の教えにも通じます。「舞台の上で何か新しいものを加えたり、クリエイティブで意外なものを持ってくるな」という指導は、相手を無視した芝居を避けるためです。
「何かを加える」という方向性の芝居は、イメージの演技です。そして、もし新しいものを加えようとして「できなかったら」、俳優は「またできへんかったわ」と思い、楽しくなくなってしまうのです。
「減らす」演技の驚くべき効果
対照的に、「ビア・ネガティブ」、つまり「減らす」演技は、俳優に自由と達成感をもたらします。
指導者は強調します。
「意識して何かをするのではなく、意識して何をやめるかを考えてください。」
重要なのはプロセスです。無意識に同じことを選んでいる「癖」を意識的にやめることで、新しい可能性が生まれるのです。
実践!「やめる」ことで広がる選択肢
このビア・ネガティブの概念は、「アンタレス駅」のシーンの稽古で実際に試されました。
俳優たちは、止まること、相手を直視し続けること、腕を下げること、お辞儀、前を向いて話を聞き続けること、下を向くこと、無表情であることなど、無意識にやってしまっている様々な「癖」をやめる試みに挑戦しました。
自由と情報量の爆発
「やめる」ことを意識的に行った後、俳優の一人はこう語りました。
「なんか今まで無理なことがない。なんだろう。今まで選択肢があると思ってたんですけど、今は何かちゃんとなんか選択肢があったなと思って。」
今まで意識していなかった選択肢が目の前に現れたのです。
指導者は、この変化を次のように評価しました。
「受け取りの情報量が非常に多くなったなと感じます。顔の角度とか呼吸も変わってましたし。」
俳優たちが自由になったと感じたのは、「やめる」ことは達成可能だからです。新しいことを加えること(クリエイティブ)が成功するか分からない恐怖に対し、「やめる」ことはすぐにでき、達成感があるため、不安がないのです。
演技は体が先です。やめることは体が先に動く。新しいポーズを考えようとすると、脳でラグが発生し、体が遅れる。しかし、「それやめて」と言われたら、すぐに体が反応し、次の行動が連鎖的に始まるのです。
飽きることの重要性
指導者は、師匠から言われた言葉を引用します。
「森本君、お芝居ってのはどれだけ飽きれるかだよって。飽きた数だけ次のものが始まるから、次の芝居が始まるから面白いんだよって言われた。」
グロトフスキの「減らしていく、やめていく」というニュアンスは、「飽きる」という行為と一緒なのです。一つの行動に固執せず、それを「やめる」ことで、次の行動へと連鎖させていく。この「やめる連鎖」が、俳優を自由にし、予測不可能な新しいシーンを生み出すのです。
「加える」と「やめる」の心理的な対比
演技を「加える」方向で考えると、それは抽象的な思考です。新しいこととは何か、クリエイティブとは何か、という抽象的な概念を追い求める。
一方、「やめる」ことは具体的です。
「私ここでいつもセリフ止まって言ってるわ」
「いつもギターを弾いてないから、これをやめよう」
これらは明確で、すぐに実行可能です。ハードルが下がり、達成感が生まれるから楽しい。
加える演技は、俳優の頭が先行し、その「えー」「どうしよう」という思考のラグが芝居の遅延につながります。しかし、やめる演技は体が先、体が動けば気持ちは動く。
観客も参加する「やめる」習慣
この「ビア・ネガティブ」の習慣を身につけることは、劇団全体で取り組むべきテーマとして強調されました。
もし、稽古を見ている人が「ずっと歩いているな」と思う人がいたら、**「歩くのやめてみて」**と声をかける。そうすることで、俳優は「あ、歩いてたんや」と無意識の行動に気づき、「歩くのをやめる」という具体的な行動によって、新しい行動が連鎖的に始まるのです。
「やめることはすぐできるからどんどん言ってあげたいと思う。やめてみて、やめてみて、やめてみてって言ったらどんどん変わってなって。」
結果主義からプロセス主義へ
指導者は、俳優が「結果」を重視した発言をした際、プロセスを重視するよう強調しました。
「プロセスにフォーカスいかないとリザルト演技だよ」
結果ばかりに注目し、プロセス(なぜそうなったか)を疎かにすると、グロトフスキが避けた「加える」演技に陥りやすいのです。
今回の稽古の核は、「何を意識してやったか」ではなく、「何を意識してやめたか」。この問いが、俳優たちを抽象的な概念から引き離し、具体的で即効性のある身体的な変化へと導いたのです。
結び:重い鎧を脱ぎ捨て、自由へのステップを踏み出す
今回の劇団天文座の稽古は、演技の根本原理を見つめ直す深い時間となりました。「ビア・ネガティブ」は、一見するとネガティブな言葉ですが、その本質は自由への道です。
何かを足し算し続けるという苦しいクリエイティブな思考から解放され、自分を縛っている無意識の癖を意識的に「やめる」ことによって、俳優は瞬時に、そして具体的に、舞台上の可能性を広げることができるのです。
これはまるで、重い鎧を脱ぎ捨てるようなものです。鎧(無意識の癖や義務感)を着ている間は、新しい動きをしようにも体が動きません。しかし、鎧を一つ一つ「やめて」減らしていくことで、体が軽くなり、その場で湧き出た衝動に従って自由に行動できるようになるのです。
イェジー・グロトフスキが提唱した「ビア・ネガティブ」は、演技における革命的な視点です。俳優が何かを「する」のではなく、何かを「しない」ことによって、真の表現に到達する。この逆説的な真理は、劇団天文座の稽古場で確かに息づいています。
私たちは、この稽古を通じて得た「やめる勇気」を胸に、本番に向けて更なる進化を遂げていきます。
今後も劇団天文座の活動にご注目ください。ありがとうございました。






