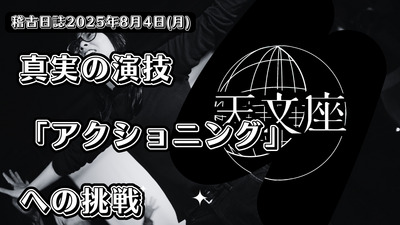
25人が紡ぐ物語:真実の演技「アクショニング」への挑戦
私たち劇団天文座が現在制作中の新作舞台は、これまでの演劇の常識を覆すような壮大な挑戦をしています。25人もの登場人物が織りなす複雑な物語と、ジュディ・ウェストンの「アクショニング」という演技アプローチを軸に、真実の表現を追求する私たちの取り組みをご紹介します。
🎭 第一章:人生という舞台での「挑戦」
私たちの人生は、まるで壮大な舞台の上にいるかのようです。キャスト陣それぞれの「これまでで一番挑戦したこと」を聞くと、共感や学びが詰まった経験談が浮かび上がりました。
💫 メンバーたちの挑戦体験
コミュニケーションへの挑戦 ある俳優は、高校時代に「女子としか喋ってこなかったため、男子に話しかけること」が最大の挑戦だったと語ります。周りからは「やばい奴」と思われないかと不安を抱えつつも、全生徒の前でトップバッターとして発表しなければならない状況に直面。義務的に感じながらも「自分もやってみたかった」という内なる願望があったと振り返ります。この経験は、その後の彼女に自己嫌悪の念を残しながらも、新たな一歩を踏み出す勇気を与えました。
独立への挑戦 別の俳優にとっては、「一人暮らし」が最も大きな挑戦でした。漠然とした憧れから始めた一人暮らしでしたが、実際には「お金はかかるし、洗濯とか料理とかその家事の知識が全くない中、すごい調べまくって」という現実に直面。本を買うにも、生活用品を揃えるにもお金がかかり、「ATMがそこ尽きるぐらいまで全部買って」、不安を抱えながらも乗り越えた経験は、新しいことへの一歩を踏み出す際の「不安な挑戦」という感覚を教えてくれました。
演劇との出会いという挑戦 ある俳優は「この関西に来て演劇を始めたこと」を人生最大の挑戦だと語っています。元々「人前に出るのが苦手で喋るのも本当に嫌」な性格だった彼が、舞台と出会ったことで「こういう世界もあるんだ」と新しい可能性を見出しました。親元を離れ、人生をかけるほどやりたいことに出会えたこと、そしてそれを許してくれた両親への感謝、演劇を通じて出会えた人々への感謝を抱き、「生涯かけてお返ししていきたい」という強い思いを抱いています。
進路選択への挑戦 高校から大学ではなく専門学校への進学を親に納得させるため、「自分からこの専門に行きたいと、めちゃめちゃいろんな学校を調べて、その上でもこの学校がいいんだっていうのをはっきり証明した」ことが一番の頑張りだったという声もありました。
🎯 挑戦から見えてくる真実
これらの話から見えてくるのは、私たちの人生が「挑戦の連続」であるということです。どんなに困難に思えることでも、一歩踏み出して「行動」してみれば、案外できることがたくさんある、という共通の真実があります。しかし、人間は恐怖心から行動をためらいがちである、という側面もまた事実です。
🎬 第二章:演劇における真実の追求「アクショニング」
私たち俳優の仕事は、舞台の上で演技をすることです。演技とは、単に台詞を暗記して言うだけではありません。舞台の上で私たちは「その役の登場人物として行動をしていく必要がある」のです。この「行動の積み重ね」こそが演技であり、その行動の結果として感情が生まれる、というのが、今回深く掘り下げていくジュディ・ウェストンの**「アクショニング」**という演技アプローチの根幹をなす考え方です。
🔥 アクショニングの核心:感情は行動から生まれる
「アクショニング」とは、俳優が「悲しい」「楽しい」「嬉しい」といった抽象的な感情を直接的に表現しようとするのではなく、**「具体的な行動(動詞)」**に焦点を当てることで、より自然で説得力のある演技を引き出すアプローチです。
従来のアプローチの問題点 例えば、一般的に「怒っているから大きな声を出す」と考えがちですが、アクショニングではそうではありません。これは感情を「説明している」に過ぎず、観客には「嘘の演技」と見抜かれてしまいます。ジュディ・ウェストンは、感情は「行動の結果として自然に湧き上がる」ものだと考えました。
アクショニングのアプローチ では、どうすれば良いのでしょうか?それは、**「相手に何をさせるか」**という具体的な「他動詞」で演技を考えることです。例えば「怒っている」という感情を表現したい時、「大きな声を出す」という結果ではなく、その感情の裏にある行動として「相手を非難する」「相手を馬鹿にする」「相手を陥れる」といった動詞を考えるのです。あるいは「助けを求める」「懇願する」といった動詞も考えられます。
このアプローチにより、演技に「明確な方向性」が生まれます。感情を無理に作り出すのではなく、目的を持った「能動的な行動」をすることで、感情が自然に湧き上がることを促し、結果として「本物で説得力のある演技」が実現するのです。演技は「嘘をつかない機会」であり、俳優が「自分自身の真実を表現すること」を目指します。例えば、俳優が「怒ってみて」と言われて演技しても、観客にはそれが「全員嘘」だと見抜かれてしまいます。重要なのは、感情を「作る」のではなく「生み出す」ことなのです。
このアクショニングという考え方は、ジュディ・ウェストン自身が映像系の演技コーチであったことから、リアリズムの演技を目指すものです。特に映像作品では、舞台よりも微細な表現が求められるため、サブテキストやアクショニングの基礎を身につけておくことは、芝居のクオリティを格段に向上させることにつながります。
🛠 アクショニングを支える具体的な要素
📚 豊富な動詞リストの活用 ジュディ・ウェストンの著書『演技のインターレッスン』には、約200個ものアクション動詞リストが掲載されています。この本は、俳優が演技を続けていく上で一度は手に取るべき良書とされていますが、現在では価格が高騰しており、入手困難な状況です。それでも、中古書店などで見つける機会があれば、ぜひ探してみる価値があるとのことです。
🎭 サブテキストの探求 アクショニングにおいて、セリフの裏に隠された意図や感情、すなわち**「サブテキスト」**を深く掘り下げることが非常に重要です。演出家は「お客様っていうのは俳優のセリフを聞きに来てんじゃねえんだよ。サブテキストを聞きに来てんだよ」と強調します。
日常においても、私たちは内心とは異なる言葉を発することがあります。例えば、理不尽な状況で内心では「ぶっ殺す」と思いつつも、実際には「すいません」と頭を下げる、といったギャップです。この「お前の頭おかしいんじゃないか」という言葉がサブテキストであり、実際の行動は「頭を下げる」である、という構造を理解することが、演技の奥行きを生み出します。サブテキストは基本的に「相手の中で生まれるもの」であるため、相手の反応を正確に捉えることが求められます。
⚡ プロセス重視の演出 アクショニングは、結果としてのセリフよりも、そのセリフに至るまでの**「過程(プロセス)」**を重視します。これは「リザルト演技」(結果を重視する演技)とは対極にある考え方です。俳優は、ただセリフをどう言うかではなく、「なぜそのセリフが出てくるのか」という過程に集中することで、より自然でリアルな演技が生まれます。
稽古の現場でも、演出家は俳優に対して「相手にセリフ言ってんのに、相手の反応があってから次の行動になるじゃないですか」と指摘します。俳優が自身のセリフを言うことに集中しすぎて、相手の反応を無視してしまうと、それは「結果だけ」の演技になってしまいます。これは「もったいない」ことであり、観客にも「無視した」と見抜かれてしまうのです。
🤝 監督と俳優の信頼関係 ジュディ・ウェストンは、監督が俳優を単なる指示の受け手ではなく、「独自な視点を持つアーティストとして尊重すること」を強調しています。俳優が安心して「リスクを犯かし、自由に役柄を探求できる環境」を築くことが極めて重要です。
ウェストン自身も、監督が「演技を体験すること」で、俳優の感情的なプロセスや課題への共感を深めることを推奨しています。舞台に立ったことのない者が監督をすることはあっても、俳優の気持ちが分からなければ真の指導はできません。これは、音響や照明といった他の分野でも同様で、自らが経験することで、その分野の専門家の気持ちを理解し、経験値を高めることができます。
🎨 実践的なテクニック
📖 脚本分析 脚本を分析する際には、ト書き(脚本に書かれた演出や感情の指示)にある形容詞や感情的な指示を一旦削除し、キャラクターの行動や感情的な歴史を深く探求します。常に「なぜ」「なんで」「どうして」という問いを立て、結果に行きつかないプロセスを積み重ねていくことが、脚本分析の肝となります。
🎪 リハーサル 稽古(リハーサル)では、即興や「アズ・イフ(as if)」といった手法を取り入れ、俳優が役柄を深く探求し、共演者との繋がりを築く場とします。特に、相手が今何をしているか、どう反応しているかという「相手を見る」視点は、自然な演技を生み出す上で不可欠です。
🎯 キャスティング キャスティングにおいて最も重視されるのは、「単に個の演技力」だけではありません。それ以上に「俳優間の関係性や化学反応」が重要視されます。演出家は、「下手くそだからこの役とか、うまいからこの役とかそういうのでは一切ない」と断言します。最も大事なのは「お客様が最高」と感じ、お客様の人生を変えるような作品を届けることであり、そのために「最高の状態をお届けできるように」キャスティングするのです。まるでバンドのメンバーを選ぶように、「それぞれのやっぱり自分の楽器に合った役」を選ぶことが、作品全体の調和を生み出すとされています。監督は、俳優の「長所しか見ない」という哲学を持ち、短所ではなく、その人が持つ最も良い部分を活かすことを重視しています。
🌟 第三章:25人の登場人物が織りなす壮大な物語の舞台裏
現在、私たち劇団天文座で制作が進められている新作脚本は、これまでの演劇の常識を覆すような壮大な挑戦をしています。
🤖 AIも驚く25人の登場人物
この新作脚本は、なんと25人もの登場人物が登場するという異例の規模で制作されています。驚くべきことに、AIに脚本の評価を依頼した当初は、「登場人物が多すぎます」「役割を兼ねて絞ることをお勧めします」と指摘され、わずか60点という低評価だったと言います。しかし、演出家は「それができたら苦労じゃねえわ」「わしの才能やからね」と、この挑戦に真っ向から向き合いました。そして、2幕が書き上がった時点で再度AIに評価させたところ、なんと**「この25人の登場人物をうまく使いました」と100点満点**の評価を得たのです。これは、一つ一つの役に意味を持たせ、アンサンブルに頼らない「地獄のような」作業だったと語られますが、座長の確固たる信念と努力が実を結んだ瞬間と言えるでしょう。
🌍 物語の世界観と深遠なテーマ
この物語は、非常に複雑で重層的な構造を持っています。キーワードとなるのは「忘れられた記憶」「壊れていく世界」「個人の選択」です。
物語の中心には、2つの世界が存在します。一方の主人公が世界を破壊しようとし、もう一人の人物がそれを修復しようと奔走するという展開は、観客を強く引き込むでしょう。この作品の演出家は、単なる悲劇を見せるのではなく、悲劇に至るまでの主人公の**「どれだけ美しくもがき苦しむのか。この過程を私は見たいの。最高の悲劇をこの手で演出したいのよ」**という、深遠なテーマと情熱を抱いています。
特に注目すべきは、主要人物の一人である川崎ユウトの役割です。彼は物語を「破壊することによって主人公が変わる」という重要な役割を担いますが、物語の「主人公はあなた(観客)」であり、川崎ユウト自身はヒーローとして描かれていません。むしろ、物語の構造上、「一貫したテーマ」として「加害者」の側面を持つ人物として描かれており、観客に安易な感情移入をさせない工夫がされています。これは、誰もがヒーローではないという現実を突きつけ、従来の物語の枠を壊す試みと言えるでしょう。
物語の根底には、10年前に中止になった文化祭と劇場の取り壊しという過去の出来事があり、登場人物たちはその「失われた言葉」や「記憶」を取り戻そうと奮闘します。しかし、彼らの行動は時に「自己満足」と批判され、また、人間関係の複雑さや「悪意のない悪意が一番人を追い詰める」という真実も描かれています。これは、人が目を背けてきた「本当のこと」に向き合う物語でもあるのです。
🎭 キャスティングに込められた演出家の意図
この25人の登場人物に対するキャスティングは、単に「演技が上手いか下手か」で決まるものではありません。前述の通り、「俳優間の関係性や化学反応」が重視され、それぞれの俳優が持つ「楽器に合った役」が選ばれます。
例えば、ある役者には「説明ゼリフがクソほど多い」役が割り当てられますが、演出家は「説明しちゃって欲しくない」「言葉で会話でやって欲しい」という高度な要求をします。これを実現するには「すごい技術がいる」とされ、経験値の豊かな俳優がその役に選ばれています。
🎪 監督から見た俳優たちの個性と演技
演出家は、俳優一人ひとりの演技の特徴を深く理解し、その個性を最大限に活かすようキャスティングしています。
🌟 高い技術を持つ俳優たち
- 川村: 説明的な台詞を「会話」として成立させる高い技術と豊富な経験を持つ。
- Bさん: 「クッパ」(大雑把で力強い演技)もできるが、繊細な表現も可能であり、特に「含みがある」演技ができる稀有な存在と評価されている。彼女は「芯の強い女性」という監督の作品のテーマにも合致するタイプ。
🎨 繊細さを追求すべき俳優たち
- 福岡: 「繊細さ」を追求すべき俳優であり、力強く見えがちだが、本質は繊細な芝居に向いている。芝居の計算や引き算ができるタイプであるべきだと指導されている。
- マグロ: 「繊細な芝居」ができるようになり、声も響くため、一本体を任せたいと考えるほど評価が高い。
- 中原: 繊細な持ち味を持つ俳優。
📈 成長が見られる俳優たち
- 俳優A: 以前は「クソクッパ」と言われるほど力強い演技だったが、最近は繊細さが出てきており、成長が見られる。
- 俳優B: 現状はまだ「クッパ」寄りの演技であり、繊細さに磨きをかける必要があるとされている。
🎭 独特のタイプを持つ俳優たち
- Aさん: 悲劇的な声を持ち、「悲劇のクッパ」という独特のタイプ。
- Bさん: クッパに見えて繊細な演技ができる。
- :Cさん クッパ寄りのタイプ。
監督は、俳優が「自分の演技を、セリフを言うことに集中しすぎ」ていると指摘し、相手の反応を「見ること」の重要性を繰り返し強調します。稽古場では、俳優の身体の使い方、特に首の傾きや目線、呼吸など、具体的な身体表現の指導が行われています。これは、呼吸が通りやすい姿勢を保つことで、声が出やすくなり、演技の質が向上するという考えに基づいています。また、「アレクサンダーテクニック」のような、緊張によって現れる身体の状態を改善し、マイナスをゼロに戻すアプローチも重要だと考えています。
✍️ 第四章:物語を紡ぐ過程と演出家の哲学
この新作脚本は、現在2幕まで書き終わり、およそ8000字に達しています。全体で3幕構成を予定しており、残りの部分で物語がクライマックスを迎えます。座長は連日深夜まで執筆を続け、休憩を挟むとはいえ、ぶっ通しで書き上げることもあります。時には、3時間で8000字を書き上げるような速筆を見せることもありますが、今回の25人の登場人物を「うまく使う」という挑戦があったため、ペースは遅めだったと語られています。
🎭 演出家の創作への情熱
監督は、この物語を通じて「最高の悲劇を演出したい」という強い願望を抱いています。彼は、「物語を創作した後、台本は作者から離れる」ものとしながらも、自らの演出で「作者も驚くような答え」を見つけることが「腕のいい演出家の役目」だと考えています。そして、彼の「ただ一つの願い」は「もう一度新しい物語を生み出すこと」なのです。
🎨 引き算の演技という哲学
彼の演出哲学の根底には、「引き算の演技」という考え方があります。特に説明的な台詞においては、ただ説明するのではなく、いかに繊細に扱い、サブテキストをどれだけ作れるかが重要になります。これは、キャラメルボックス劇団の俳優たちの演技を例に挙げながら語られており、力強く見えても実は繊細な演技をする役者こそが、彼の求める理想に近いとされています。監督自身の作品には、「芯が強く、タフな女性」のキャラクターが多いのも特徴的です。
🎯 キャスティングの深い意図
キャスティングの意図についても、監督は「なぜね、その役を選んだかっていうのは絶対意図はあるんでね」と語ります。例えば、観客に語りかける役では、誰が語りかけるかによって観客の反応が変わることを計算し、繊細な声を持つ俳優を選ぶことで、「聞きたくなる」という効果を狙っていると明かしています。これは、彼の作品が単なる娯楽に留まらず、観客の心に深く響く「大作」であることを目指している証拠と言えるでしょう。
🌈 終わりに:物語が続く限り、挑戦は終わらない
今回の記事を通じて、私たちは、個人の日常的な挑戦から、演劇という芸術分野での「真実の表現」の追求、そして壮大な物語の創造まで、あらゆる局面で「行動」がいかに重要であるかを改めて認識しました。
ジュディ・ウェストンのアクショニングが教えるように、感情は行動から自然に生まれるものです。そして、舞台の上で「嘘をつかない」演技を追求するように、人生においてもまた、表面的な結果だけでなく、その過程に集中し、真実を見つめ、行動していくことが、私たち自身の物語を豊かにし、感動的なものへと導いてくれるのかもしれません。
25人もの登場人物が登場する新作舞台は、まさに挑戦そのものです。AIに「多すぎる」と指摘されながらも、それを「うまく使った」と100点満点を獲得したように、困難に見えることでも、信念を持って「行動」し続ければ、必ず道は開けます。
私たち一人ひとりが、自分の人生という舞台の上で、自分の感情の「サブテキスト」を探り、そして「嘘のない」行動を選択していくことで、より深く、より豊かな物語を紡ぎ出すことができるでしょう。この舞台が完成し、観客の皆さんの人生に新たな感動と「挑戦」の種をまくことを心より願っています。物語はまだ終わっていません。そして、私たちの挑戦もまた、続いていくのです。






