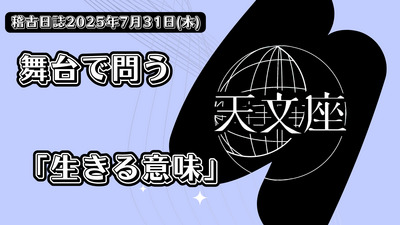
舞台で問う「生きる意味」
舞台の照明が落ち、静寂が劇場を包む。そこには答えではなく、問いが残されている。「人として生きるとは何か」「正義とは何か」——私たちの劇団で1ヶ月半にわたって開催されたワークショップは、単なる演劇技術の習得を超えた、人間存在の根源に迫る旅路となった。
哲学と演劇が交差する場所
このワークショップの核心は、参加者一人ひとりが「何のために生まれ、どのように生きるべきか」を深く考える場を提供することにあった。それは単に生物学的な生存を超え、目的や価値、幸福を追求する精神的な旅路としての人生をどう歩むのかという、私たち全員が抱える普遍的な問いだった。
古代ギリシャのアリストテレスから現代の脳科学まで、様々な思想と科学的知見を横断しながら、参加者たちは問いを探求した。アリストテレスが説く「理性の卓越」、カントの「自己立法」の能力、サルトルの「実存は本質に先立つ」という主張——これらの哲学的概念が、演劇という表現形式を通じて新たな意味を帯びていく。
特に興味深かったのは、仏教の「無我」の概念と演劇における「自己意識から他者意識への移行」との類似性だった。固定された自己の実体を否定し、他者への慈悲の心を持つことが良き生につながるという仏教的な視点は、役者が自分を捨てて役になりきるプロセスと驚くほど共鳴していた。
舞台の上で問われる正義という複雑な概念
ワークショップでは正義についても多角的に議論されたが、それは単なる理論的な探求にとどまらなかった。参加者たちは演技を通じて、正義の概念を身体で体験することになったのだ。
功利主義の「最大多数の最大幸福」とカントの義務論的正義観の対立を、参加者たちは実際の演技の中で表現した。たとえば、一人の登場人物を救うために多くの人を犠牲にするシーンでは、役者たちは自分の感情と論理の間で揺れる複雑な心理状態を表現しなければならない。この時、頭で理解していた哲学的概念が、突然リアルな感情として立ち現れる瞬間があった。
特に印象深かったのは、アンパンマンの行為を演技で再現した場面だった。カント哲学的に「最も正しい」とされる自己犠牲的な行為を実際に演じてみると、「全員がアンパンマンだったら倫理が崩壊するのではないか」という逆説的な問いが、演者の身体を通じて観客にも伝わってくる。理論として理解することと、実際に演じることの間には、大きな感情的な隔たりがあることを参加者たちは発見した。
ロールズの「公正としての正義」やキャロル・ギリガンらの「ケアの倫理」といった現代の正義論も、演技練習の中で具体的な人間関係として表現された。戦争や災害といった極端な状況を舞台上で再現する際、参加者たちは台本を読むだけでは感じられない道徳的なジレンマを体験した。
演技を通じて正義を探求することで、参加者たちは理論では捉えきれない正義の多義性を身体で理解していった。舞台の上では、正しい答えなど存在しない——あるのは、その瞬間の登場人物の選択と、それに対する観客の共感や疑問だけだった。
9月公演劇団天文座イマーシブシアター「あなたが書くまで、何も始まらない」が描く未来への問い
理論的な探求と並行して、参加者たちは9月公演劇団天文座イマーシブシアター「あなたが書くまで、何も始まらない」の稽古に取り組んだ。この作品は「失われた日常の言葉」や「沈黙」をテーマに、記憶をなくした登場人物たちが未来を探し求める姿を描いている。
最も印象的だったのは「白紙の台本」という仕掛けだった。書かれていないはずのページが、ある登場人物の「涙」と「汗」によって「未来の思い出」として浮かび上がる——これは「言葉には重さがある」というテーマを視覚的に表現する、詩的で力強い演出だった。
観客が自身の物語を書き、物語の「終わり」を決めるという参加型の要素も取り入れられ、観客もまた作品を完成させる共同創造者となった。これは、人生における主体性と選択の重要性を体現する演出でもあった。
演出という対話の芸術
ワークショップでは2つのチームに分かれ、それぞれ異なる演出家のもとで表現を探求した。前田さんのチームは「失敗はない」というスタンスで役者の自由な発想を促し、サブテキストが表面に現れるような極限状態での表現を追求した。一方、小林さんのチームは役者の潜在能力を最大限に引き出し、演出家の意図を先読みするほどの信頼関係を築いていた。
この違いは、人と人との関係性の多様性を象徴していた。同じ作品でも、異なるアプローチによって全く違う表現が生まれる——これは人生そのものの多様性と重なる。
観客からは「わかんないけど面白い」「全然わかんないけど世界観がある」「台本の言葉の重さが気になる」といった率直な感想が聞かれた。完全に理解できなくても心に響く何かがある——それこそが優れた芸術の証左かもしれない。
個人的な目標という生きる意味
ワークショップの締めくくりとして、参加者それぞれが「人としてどう生きていきたいか」という個人的な目標を共有した。彩佳さんは好きなことを続けながら、おばあちゃんに孫の顔を見せたいという家族への愛を語った。マグさんは治療を経てラップアルバム制作という音楽への情熱を語り、りっくんは見た目で人を判断するバイアスから自由になりたいという自己変革への意志を表明した。
これらの目標は、どれも小さくて大きな、個人的で普遍的な願いだった。哲学的な問いの答えは、結局のところ、こうした一人ひとりの具体的な生き方の中にこそ見つかるのかもしれない。
AIとともに進化する創作
興味深いのは、この劇団がAI(Gemini)を脚本の評価に活用していることだった。当初の「説明的すぎる」脚本から「今後の展開が難しくも奥深い」作品へと進化させる過程で、人工知能も創作の一部を担っている。これは現代における創作活動の新しい形を示唆している。
人間とAIの協働もまた、「人として生きること」を問い直す要素の一つなのかもしれない。技術の進歩によって人間の独自性が問われる時代だからこそ、人間らしさの本質を探求することがより重要になっている。
終わりなき探求という答え
1ヶ月半から2ヶ月にわたるワークショップを通じて、参加者たちの成長は目覚ましかった。「全然違う」表現ができるようになったという変化は、人間の可塑性と成長の可能性を物語っている。
「人として生きること」への答えは、おそらく単一の解答として存在しないのだろう。それは「自らの存在の意味を問い、他者と共に善を探求し、より公正な世界を目指す終わりなきプロセス」そのものなのかもしれない。
多様な思想の緊張関係の中で見極め、対話し、問い続けること——これこそが人として生きることの核心であり、演劇という芸術形式が持つ本来の力なのだ。
舞台の上で問われた問いは、観客席に、そして日常生活に持ち帰られる。来年6月に予定されている次回のワークショップ公演もまた、新たな問いを投げかけることだろう。なぜなら、問うことこそが人間であることの証だから。
答えのない問いを抱えて生きること。それが、私たちが舞台で、そして人生で学んだ最も大切なことかもしれない。






