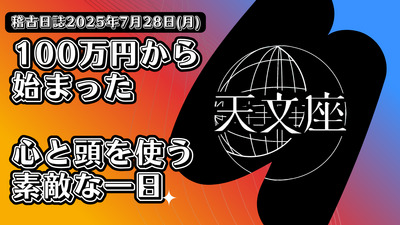
100万円から始まった、心と頭を使う素敵な一日
~思考力と演劇が出会った特別なワークショップ~
「もし100万円あったら、何に使いますか?」
こんな質問から始まった今回のセッションは、最初から最後まで驚きと発見に満ちた、本当に充実した時間でした。参加者の皆さんの答えを聞いているだけでも、その人となりが見えてきて面白かったんです。
みんなの100万円、どう使う?
スマホと病院代に現実的に使いたい人、北海道や長野への友達との旅行を夢見る人、そして一軒家を買いたい(でも100万円じゃ足りないよね、というツッコミ付き!)という夢いっぱいの人まで、本当に様々でした。
特に印象的だったのは、ポンキチさんの「美味しい食事と、残ったお金でゲーミングPC」という、なんとも現代的で素敵な答え。
長井寛和さんの「一人暮らしと奨学金の返済」という現実的な答えには、みんなが深くうなずいていて、きっと多くの人が共感したのではないでしょうか。
脳の不思議な仕組み:速い思考と遅い思考
この楽しい導入から、話は思考の奥深い世界へ。ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの理論について学びました。私たちの頭の中には、まるで二人の人格が住んでいるかのような、二つの思考システムがあるんです。
システム1は、まるで反射神経のように素早く働く直感的な思考。「2+2=4」なんて瞬時に答えが浮かんだり、相手の表情を見て感情を読み取ったり。車の運転や自転車に乗ることも、最初は必死に考えながらやっていたのに、慣れてしまえば無意識にできるようになりますよね。面白いことに、リンちゃんの「うるさい顔」もこのシステム1の働きだそうです。
システム2は、じっくり考える論理的な思考。「12×24」の計算や、複雑な計画立案、自己コントロールや衝動の抑制などに使われます。でも、このシステム2は「本質的に怠け者」で、できるだけエネルギーを使いたがらないんだそう。システム1が直感的な判断をシステム2に提案し、多くの場合、システム2はその提案を吟味することなく受け入れてしまうという、なんだか人間らしくて親しみやすい特徴があります。
頭の罠:認知バイアスって何?
そして、私たちの思考には様々な「罠」があることも学びました。これが認知バイアスと呼ばれるもので、実は私たちの日常生活に深く根ざしています。
飛行機事故のニュースを見た後、統計的には車より安全なはずの飛行機に乗るのをためらってしまう「利用可能性ヒューリスティックス」。自分の信じたいことを支持する情報ばかり探してしまう「確証バイアス」。結果を知った後で「最初からそうなると思っていた」と思い込んでしまう「後知恵バイアス」。
同じ内容でも提示の仕方によって判断が変わってしまう「フレーミング効果」や、利得よりも損失を強く感じてしまう「損失回避」。投資した費用や労力を惜しんで非合理的な判断をしてしまう「サンクコスト効果」は、ギャンブラーにとって特に刺さる内容だったようです。
特に印象的だったのは、座長の「正常性バイアス」の実体験。複雑骨折した足首を「行ける!」と言って運転し続けたという話には、会場がどよめきました。私たちって、異常事態を過小評価してしまうことがあるんですね。
でも、これらのバイアスは必ずしも悪いものではありません。重要なのは、まず自分がこうしたバイアスの影響を免れないという事実を受け入れること。そして「なぜ今自分はこう感じたのか」と自問する習慣をつけることで、システム1の暴走にブレーキをかけ、システム2を意図的に起動させることができるのです。
AIと一緒に考える新しい時代
現代ならではの話題として、AI時代の思考力についても深く掘り下げられました。AIの普及により、自らシステム2を使って熟考する機会が減り、認知オフロード(認知負荷の外部委託)が進む可能性があるという新たな課題が提示されました。でも、AIを思考力増強のツールとして活用することもできるんです。
座長が脚本をAIに見せて「むちゃくちゃにボロクソに評価しろ」と指示し、100点満点中6点をもらった後に「褒めて」と言って高評価をもらうという、なんとも斬新な使い方をしているエピソードには思わず笑ってしまいました。この低評価と高評価の違いや共通点を探ることで、脚本の客観的な分析ができるというのは、まさにAIを「悪魔の代弁者」として活用する優れた例ですね。
さらに面白かったのは、演劇の新しいアイデアを出すためにAIと1〜2時間も壁打ちをし、「全部それ見たことがある」と言われ続け、最終的に「あなたがしたいことはそもそも演劇ではない」とAIに言われたというエピソード。創作者の苦悩と工夫が伝わってきて、とても興味深く、同時にAIが創作プロセスにおいて貴重な壁打ち相手になることを実証していました。
いざ実践!演劇ドラフトで白熱
座学の後は、お待ちかねの演劇ワークショップ。今回はなんと、本格的なドラフト会議でチーム分け!志水さん率いる志水チームと、あかりさん率いるあかりチームに分かれて、まるで野球のドラフト会議のように「ガチ」で指名が行われました。くじ引きでの抽選もあり、参加者の皆さんが順に指名されていく様子は、見ているだけでドキドキハラハラの連続でした。
演目は「オレンジデイズ」の特定のシーン。座長は原作を6周もするほどの愛好家だそうで、その熱意が伝わってきます。この作品選択には深い意味があって、原作がある作品を扱う場合、徹底的に原作を調べることが演出家の強みになるという学びも込められていました。特に難しかったのは、手話と心の声をどう演出するかという部分。これは演出家の腕の見せ所で、システム1とシステム2のどちらが優れているかではなく、どのように使いこなすかが重要だという、午前中の学びを実践する絶好の機会でもありました。
両チーム、それぞれの輝き
志水チームでは、志水さんが演出の難しさを実感しながらも、「動と静の対比」が効果的で、役者たちの自然な関係性が観客の想像力をかき立てる素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。志水さん自身は「演出は非常に難しく、セリフを覚えることに気を取られてしまい、自分自身に焦点を当てすぎた」と反省されていましたが、観客から見ると川村さんが声を発した瞬間のリアクションから「人たちの関係性が自然と分かるように感じて、想像力をかき立ててくれた」と高く評価されていました。
あかりチームは、見ていて「すごく楽しい」演出で、特に矢次さんの素晴らしい声と存在感、台詞をしっかり覚えている姿勢が賞賛されました。あかりさん自身は「ワークショップは楽しかったが、みんなに支えられた」と感じていたそうですが、昨日学んだ観客目線を意識し、演出側と客側の両方の視点から考えることの重要性を実感したと語っていました。その努力が実を結び、観客にとって本当に楽しめる演出になっていたのが印象的でした。
座長からの心に響くメッセージ
ワークショップの最後に、座長からあかりさんに贈られた言葉が特に印象的でした。
「そろそろ卒業して欲しい」
これは、「みんなに支えられる」演出家から、
「君がみんなを支える」
演出家への成長を促す、愛情あふれるメッセージでした。演出家の仕事は、みんなが道に迷った時にその道を示すこと、つまり「みんなを助けること」だという言葉には、会場全体が静かに聞き入っていました。この意識の変化こそが、あかりさんの作品をより良いものにしていくのだという、深い愛情と期待が込められた激励でした。
温かい学びの時間
この日のセッションは、難しそうな認知科学の理論から始まって、最後は心温まる演劇ワークショップで締めくくられる、本当に贅沢な時間でした。参加者一人ひとりの個性が光り、お互いを支え合いながら学び合う姿が印象的で、こんな学びの場があることの素晴らしさを改めて感じました。
思考力を鍛えることも、演劇を通じて表現することも、どちらも「人間らしさ」を大切にした営みなんだなと、しみじみ思った一日でした。次回のワークショップも、きっと新しい発見と出会いが待っているはず。楽しみです!






